
建礼門院右京大夫 (朝日文芸文庫)
読み終えた途端、何一つ手につかない程の余韻に浸りました。
清盛の孫、平資盛を愛した平安時代の女官、右京大夫とその日々が本人の視点から綴られています。 建礼門院は平清盛の娘。右京大夫は平家黄金期の後宮で彼女に仕えた女官です。 過去を過剰に美化してないか、それにいつかは別れたんじゃ…などと考えなくもないのですが、そこを差し引いても当時の流れを知るに貴重なもの。原典は未読ながら、とにかくこの中の平資盛が強烈な印象で、その名を聞く度にこの本を想い出すようになりました。 そしてもう一人の恋人、似せ絵師でもある藤原隆信との顛末や、周囲との交流など、事細かな描写で綴られています。季節行事、文のやりとり、まるでその場に居合わせたかのような錯覚すら覚え、大満足の★5です。 ※入り組んだ登場人物に加え、最近は耳にしなくなった丁寧な言葉使いです。もしかしたらてこずる部分かも知れませんが、そこを乗り越えて読んで頂きたいです。 追記:隆信はあの源頼朝?の絵を描いた人(かも)らしいです(頼朝ではない可能性も指摘されていますが)。あとで知って「!」でした。 
婉という女・正妻 (講談社文芸文庫)
苛酷な人生を強要された女性が、誇りひとつを胸に自律的に生きた姿を、いい文章で綴っている。
わずか4歳の時、父の罪なき罪で40年間幽閉された女が、兄から四書五経を学びつつ、自分のアイデンティティーをどう守って生きたか。 竹矢来の内側に40年いて、初めて世の中というものに出て行き「川」を見たときの感銘が美しい文章で表現されていた。 閉塞状況の中で、谷秦山という学者に、運命的な恋心を抱く。 最後までプライドを捨てることなく、66歳の生涯を歩んだ婉という女から、現代人はいろいろなことが学べると思う。 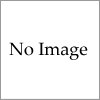
婉という女 (1963年) (新潮文庫)
久しぶりに『婉という女』(大原富枝著、新潮文庫。出版元品切れだが、amazonで入手可能)を読み返したくなって、書棚から取り出し、そそくさとページを開いたら、ほんのり甘いような古書特有の匂いがした。
40年間、幽囚の身にあった野中婉(えん)の自筆の手紙などに基づく、史実に忠実な小説であるが、女性の微妙な心理が心の襞の奥まで分け入って描かれているので、息苦しくなるほどだ。 婉が4歳の時に、母、兄弟姉妹、乳母たちとともに、高々と鋭い切っ先を空に向けた竹矢来が周りに巡らされ、番士たちが厳重に見張る屋敷に幽閉されることになったのは、土佐藩の執政(家老)として数々の大改革を成し遂げた父・野中兼山が政敵によって失脚させられ、死去した直後のことであった。 その父については、こう語られている。「父上が気鋭な、聡明な人であったこと、理想を追い求める情熱の人であったこと――。禅学から儒学にきて、夜を徹して講義を聴き、注釈も、送り仮名もない原本を手に入れて、熱心に独り注釈を試みたことなど――。22歳の若さで養父のあとをつぎ、土佐二十四万石の執政となり、死までの27年間、学問で得た知識と理想を、お仕置(政治、経綸)の上に一つ一つ実践していった人であったこと。山を崩して河の流れを変え、運河を延々と通して田圃を拓き、港を深くして大船を出入させ、山々、浦々、父上の理想の鍬の入っていない土地はない、といわれる盛んな経綸(おしおき)の数々――」、「寡黙、厳直、短慮、峻烈という『野中家の気質』をそっくり受けついでいた。父上はいつもまっすぐに前方を、未来を見ていた。失脚の日まで、過去に眼を向けようとはしなかった」。土佐の治安にいつも支障となっていた、困窮して自棄的になっている一領具足(長曽我部の遺臣である浪人たち)1万人を郷士に取り立てて、世上の不安を除いた「郷士制度」も兼山が断行した政策であった。 「延宝、天和、貞享と幽獄に年は移っていった。そうして迎えた貞享3(1686)年の夏の一日を、わたくしは生涯忘れない。――その日、わたくしたちの上に奇蹟が起った。すでに長兄、次兄もむなしくなり果て、わたくしはもう26歳になっていた。それは全く、奇蹟でなくてなんであったろう」。亡き兼山を敬慕する若者が、高知の城下から遥々と30里を踏破して遺児たちに会いにきたのである。その願いは許可されるはずもなく、空しく帰っていったのであるが、この幽獄を外部の人が訪ねてきたのは、23年間で初めてのことであった。 やがて、この婉より2歳年下の谷秦山との文通が始まる。「――わたくしは知っている。このときから、わたくしはそのひとのなかで生きはじめたのだ、と。谷丹三郎(秦山)という一人の男のなかに。貧しい、痩せた青年儒学者のなかに・・・」。文通が始まってから17年後、兼山の血を引く男子が全て幽居で死去して血筋が絶えたため、婉が43歳の時、婉たちは漸く幽獄から出ることを許される。その後も、秦山が最期を迎えるまで文通は断続的に続けられたのである。 「子も生まず、男にゆるす機(おり)もあたえられなかった、無垢というには味気ない40(歳)の乳房は、いまも娘のときに似た膨らみを持ち弾力をも失いつくしてはいなかった。燃えきることのできなかった生命がしこりとなってその内側から、抗うものを盛りあげている。空しく花を萎ませてゆく、女のいのちの一つの極点にあるような危なっかしさ、脆さが、わたくしのなかで揺れ止まない。さやぎやまないのだ。そういういまのいまが、わたくしには堪えがたくつらく、残酷であった」、「幽囚40年はわたくしからすべてのものを、すべての仕合せを奪った代りに、奇妙に若々しい肉体と不気味に揺動する心を残した。そしてそれさえもわたくしには加えられた刑罰の一つであったのだ、ということを、わたくしはいま解(し)るのであった。この空しく、虚ろな美しさ、男によって仕合せになった歴史も、不幸になった過去をも持たない、男の垢、男の膏によって汚されたことも、男の爪あとで傷ついたこともない、不犯の女の若さ、水々(瑞々)しさは、美しいよりも不気味であることをわたくしは知っている」。 「二十数年、わたくしが恋いわたってきたのはこのひとであった。わたくしがせつに欲しいと思ったのはこの幸福(しあわせ)であった。人間と人間の、男と女の結びつきにも、千差万別があるのだとしたら、わたくしと先生(秦山)のこの結びつきもまた、他のどのような深い結びつきにも劣ることのない緊密さの上にあるのだ。この結びつき、この仕合せを大切にしよう、とわたくしはこのとき秘かに思っていた」。その膝に身を投げて泣きたい思いを、生涯、必死に堪え続けた婉の心中は察するに余りある。 なお、儒者であると同時に第一級の天文学者でもあった秦山は、やがて藩の儒官として登用され活躍するが、最後は失脚してしまう。 この書の中では、時空を超えて、婉と著者の大原富枝が融け合い、一体となっている。 |

|
婉という女(土佐琵琶:谷川 桃水)2012年9月28日 高知県長岡郡本山町プラチナセンターで 同町ご出身の作家、故大原富枝さん生誕100年記念式典が 開催され、大原先生とゆかりのあった方々や、地元高校生 町民ら約300人が出席しました。 オープニング公演では 土佐琵琶奏者黒田月水さんの一番弟子で 地元で活動中の谷川桃水さんが 大原先生の代表作「婉... |
|
動物を使った比喩表現 動物を使った比喩表現を外国人に紹介します。 なにが いいと... 【今だけポイント3倍】【1000円以上送料無料】彼もまた神の愛でし子か 洲之内徹の生涯/大原富枝 植物学に興味があるのですが、 日本の文学作品の中で、登場人物が植物学者だったり... 【中古】 大原富枝の平家物語 集英社文庫わたしの古典/大原富枝(著者) 【中古】afb 子連れ・高松から車で3時間以内で行ける四国内のオススメの温泉(宿) 司馬遼氏Vs百目鬼恭氏 初心者に丁度いい古典文学はなんですか? 小学生の頃に半ば強制的に暗記させられた... 【boox限定先着クーポン配布!】婉という女・正妻/大原富枝【2500円以上送料無料】 |

マリア様がみてるマリア様がみてる 4thシーズン ED くもりガラスの向こう + Lyrics 
エジプト26日からエジプト大統領選、シシ前国防相の当選確実視 
Tower of PowerTower Of Power - So Very Hard To Go 
水雲酢mozuku 
とろサーモンとろサーモン 
オスカー・シュムスキーハンガリー舞曲第5番 vn&pf版 
とりのなん子バイクからみた夜道の風景はこんな感じだww 
亀井京子14 03 04 今夜くらべてみました 亀井京子 政井マヤ 宮瀬茉祐子 女子アナやめちゃったトリオ 奇人ぶり大公開 宮瀬の本性発掘 3月4日 |

[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
紅の舟唄 北見恭子
悲愴感
Australian Shepherd Puppies
日曜洋画劇場 / フランケンシュタイン
第8回 武田信玄の躑躅ヶ崎館
大原富枝 ウェブ
