
TOGISM 2001
篳篥(ひちりき)の澄み切った、もの悲しい音色がとても美しい。初めて聞く楽器なのに、なぜかなつかしい響きがする。
だが残念な事に、曲がどれもこれも似たり寄ったりで、しかもどうって事のない曲ばかり。いくら聞き流すだけの癒やし系の曲でも、もう少し面白味がほしいと思う。 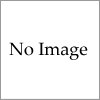
東への道【字幕版】 [VHS]
ヒロインは可憐で健気、守ってあげたい女、NO1のリリアン・ギッシュです。この作品でも決してファンを裏切ってません。見所はなんといってもグリフィス監督お得意の『最後の救出劇!!』
これを見ずしてこの映画を語るなかれ! 
危険社会―新しい近代への道 (叢書・ウニベルシタス)
本書において意味される「危険」とは、「歴史の産物であり、人間の行動や不作為を
反映したものであり、高度に発達した生産力の表れである」。 例えば、チェルノブイリが告げた原子力の「危険」、光化学スモッグや酸性雨の「危険」。 今日ならばさながら温暖化の「危険」といったところだろうか(とりあえず、エコエコ詐欺には 気づかないふりを決め込もう)。 高度に成熟した産業社会、消費社会の果て、ポストモダンとして、著者ベックが 指摘するのは、技術と自然のしっぺ返しとでも呼ぶべき「危険社会」の到来であった。 もっとも、本書の論点は単に環境問題への啓発に留まらない。 こうした「危険」は例えば政治や国家モデルのありよう、あるいは倫理の姿をも 変えてしまう、そうベックは論じる。 人によって本書をプロ市民のすすめとでも読むことがあるかもしれない。 整然とまとまったテキストとはお世辞にも称し難いものでは確かにあるが、かといって 本書における豊富な示唆は今日でもなおも有効。 例えば「危険は階級の図式を破壊するブーメラン効果を内包している」との議論。 私個人としての好悪はさておき、戦争によって危険の共有を求めるほかに道はなしとする 赤木智弘氏の議論なども案外本書の射程なのかもしれない。 
東への道 [DVD]
地味ながら、味わい深い名作です。
何度も繰り返し観たくなります。 典型的なメロドラマといえますが、 一人の薄幸な女性が幸せをつかむまでを、 じっくり丁寧に描いていきます。 主演のリリアン・ギッシュとリチャード・バーセルメスが非常に良いです。 まわりを固める脇役陣も、味のある演技をしています。 クライマックスの流氷のシーンは、迫力があり、手に汗握ります。 氷の上に寝て、髪が凍ってしまったというリリアン・ギッシュの役者魂に打たれます。 グリフィスの真価が現れた一本です。 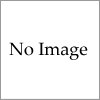
東への道 [DVD]
サイレント映画の良さって、観終わって少し時間が経って思い起こすと
演者の叫び声とか悲鳴とかが頭に残っているんですよね。 リリアン・ギッシュがどんな声かっていうのは、イメージついてます。 それだけ、画的に訴える力がすごいんだと思います。 |

じゃりン子チエアニメ DE マンザイ 「じゃりン子チエ」 5-1 
ローグ伊藤かな恵「タイニーローグ」90秒PV 
村上美香村上美香 with 中村佳苗 展『雨のふる、虹』 
ウィーンヨハン・シュトラウス2世作曲 ワルツ「ウィーン気質」 
骨折Fracture of the distal radius (橈骨遠位端骨折) june 2011 
サニー・ランドレスSonny Landreth Plays Solo Song Backstage 
オリーブREBECCA - Olive 
ふしぎ遊戯ふしぎ遊戯 Mysterious Play Episode 51 HD 2014 English Subbed |

[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
松本人志の放送室 第91回 「松本が尊敬する人」
東への道 ウェブ

